
聖徳太子ゆかりの名刹
斑鳩寺
推古天皇の時代、聖徳太子が勝鬘経、法華経などを天皇に講じられ、これに御感あった天皇より播磨国の水田を賜り、太子はこれを仏法興隆のため法隆寺に寄進されました。
後の平安時代に、この地は「法隆寺領播磨国鵤荘」となり、荘園経営の中核的存在として、政所とともに斑鳩寺が建立され、以後この地方の太子信仰の中心となりました。 斑鳩寺は法隆寺の別院として、往古には七堂伽藍、数十の坊庵が甍を並べ壮麗を極めましたが、出雲の尼子氏の侵攻で播磨が混乱していた天文十年(1541)四月七日、不慮の火災により、諸堂が灰燼に帰しました。
その後、楽々山円勝寺の円光院昌仙らにより、龍野城主赤松下野守政秀らの寄進を得て、講堂、三重塔、太子御堂(聖徳殿)、仁王門などの伽藍が復興されました。
江戸時代以降は天台宗となりましたが、今も「お太子さん」として、近郷近在から広く信仰を集めています。
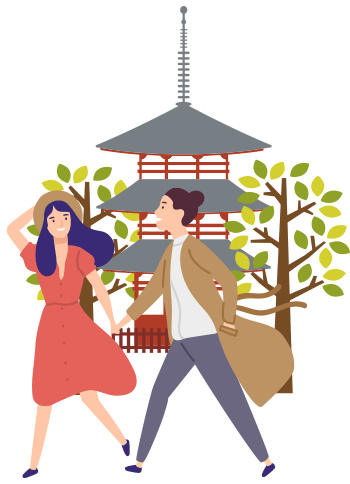

〈 三重塔 〉
[国指定重要文化財]永禄八年(1565)
永禄八年(1565)に再建され、露盤には龍野城主赤松下野守政秀が天下泰平を祈願して発願したという銘文が刻まれています。斑鳩寺伽藍のうち、天文十年(1541)の焼失後、再建された建物がそのまま残る唯一の建造物です。

〈 聖徳殿前殿 〉
[県指定文化財]寛文五年(1665)
本尊に聖徳太子十六歳孝養像を安置するお堂です。
この像は、父である用明天皇の病気平癒を七日七夜の間、日夜柄香炉を捧げ、その枕辺に立ち、常行三昧の行法を行った太子の姿で、「御孝養の御姿」といわれ、また、太子の髪が植えられていることより「植髪の太子」と称されています。
本殿は天文十年に全焼。天文二十年(1551)に再建、寛文五年(1665)に修造。大正五年(1916)には中殿及び法隆寺夢殿を模した奥殿(八角二重円堂)が増築されました。
基本情報
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤709 |
| 入場料 | 入場無料、宝物殿一人300円(団体250円) |
| 電話番号 | 079-276-0022 |
